こんにちは。統合失調症を抱えながら障害年金を受給している方や、申請を考えている方にとって、「2級と3級ってどう違うの?」という疑問はとても大きいですよね。私も調べてみるまで、「どんな基準で決まるの?」とか、「どうしたら2級になるの?」といったことがよく分かりませんでした。
この記事では、統合失調症の障害年金における2級と3級の違いについて、できるだけ分かりやすくお話ししていきます。
障害年金の基本、まずはおさらい
そもそも障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
-
障害基礎年金(国民年金)
- 1級と2級のみ(3級はなし)
- 自営業やフリーランス、学生などが対象
-
障害厚生年金(厚生年金)
- 1級、2級、3級がある
- 会社員や公務員が対象
統合失調症で3級の年金を受け取っているということは、厚生年金に加入していた時期に初診日があったということになりますね。
では、2級と3級の違いはどこにあるのでしょうか?
2級と3級の基準の違い
障害年金の等級は、「日常生活や仕事にどれくらい支障があるか」で決まります。統合失調症の場合は、**「精神の障害による等級判定ガイドライン」**が基準になっていて、それに沿って審査されます。
-
2級の基準
- 日常生活がほぼ一人ではできない
- 仕事ができるレベルではない(基本的に就労不可)
- 他人の助けがないと生活できない
-
3級の基準
- 労働が難しいが、日常生活はある程度できる
- 仕事ができても、配慮や軽い業務に限られる
- 一人暮らしはギリギリできるが、社会的なつながりが希薄
つまり、「日常生活すら大変で誰かの助けが必要」なら2級、「日常生活はなんとかできるけど、働くのは難しい」なら3級というイメージです。
具体的な判断ポイント
もう少し具体的に、どんな状態なら2級や3級になるのか、例を見ていきましょう。
2級のケース
- 外出がほとんどできない(家に引きこもっている)
- 食事や着替え、入浴などの日常生活が1人では難しい
- 家族などのサポートがないと生活できない
- 仕事をすることができない(就労経験がない、または続かない)
- 妄想や幻覚がひどく、現実と区別がつかないことがある
3級のケース
- 週に数回の外出はできる(ただし短時間)
- 食事や着替えなどは一応自分でできる
- 一人暮らしがなんとかできるが、社会的な関わりは少ない
- 軽作業の仕事ならできるが、一般的な仕事は無理
- 妄想や幻覚はあるが、コントロールできることが多い
こうして見ると、「どこまで生活が自立しているか」が大きなポイントになっていることが分かりますね。
2級と3級の間のグレーゾーン
でも、実際のところ「2級か3級か微妙…」というケースもあります。
たとえば、
- 家事は一応できるけど、調子が悪いと寝たきりになることがある
- 仕事はできないけど、たまに短時間のバイトができる
- 家族のサポートがあれば生活できるけど、一人暮らしは難しい
こういった場合、審査する人によっては2級になったり、3級になったりすることがあります。診断書の書き方や、主治医の意見によっても判断が変わることがあるので、「自分がどれくらい困っているか」をしっかり伝えることが大事です。
2級を取るにはどうしたらいい?
もし3級の認定を受けていて、「本当はもっと生活が大変なのに…」と感じるなら、更新時にもう一度申請してみるのも一つの方法です。
- 主治医に「日常生活の困難さ」を詳しく伝える
- 診断書に「生活が一人では難しい」と明記してもらう
- 生活状況を詳細に書いた申立書を提出する
特に、診断書に「日常生活において著しい制限がある」と明記されるかどうかがポイントです。
まとめ
統合失調症で障害年金を受給する場合、2級と3級の違いは**「日常生活がどれくらい困難か」**で決まります。
- 2級は「一人で生活するのが難しく、誰かのサポートが必要」
- 3級は「働くのは難しいけど、生活はなんとかできる」
もし「3級だけど、実はもっと生活が大変…」と感じるなら、診断書や申立書を工夫して、次回の更新時に再審査をお願いするのもアリです。
統合失調症を抱えながらの生活は大変ですが、障害年金をうまく活用して、少しでも安心して暮らせるようにしていきましょう。
あなたの生活が少しでも楽になりますように。
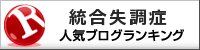
コメントを投稿
別ページに移動します